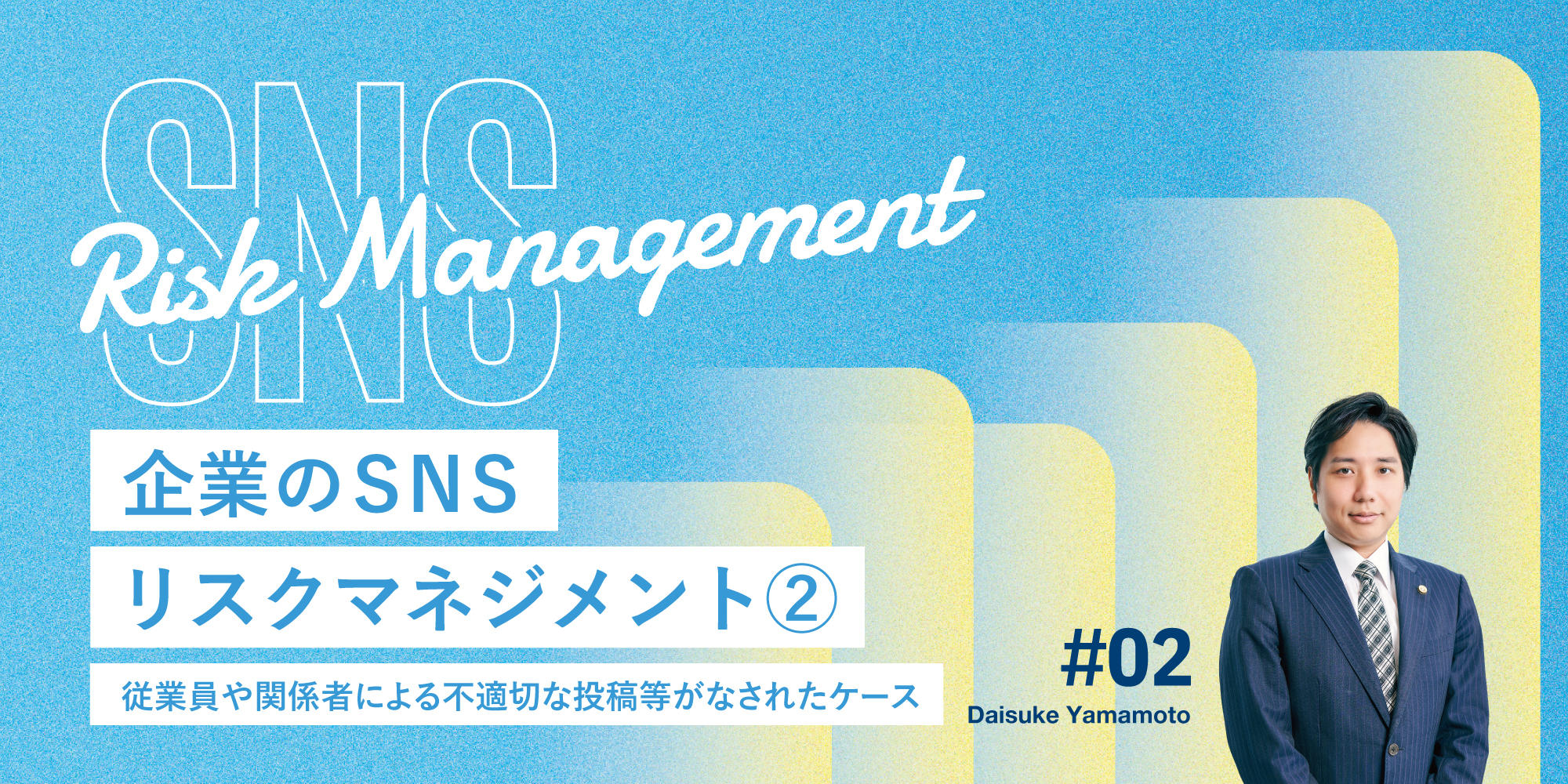企業のSNSリスクマネジメント①(第1回)
概要
現代において、企業(会社だけでなく、団体や個人事業主なども広く含みます。)によるSNSの活用は、広報、知名度・イメージ向上、採用活動など、多様な面で極めて重要なツールであると認識されるに至っています。
その一方で、SNSは常に、炎上や秘密情報の漏えいなどのリスクと隣り合わせであり、場合によっては、長年にわたって積み上げてきた信頼が一瞬にして損なわれてしまったり、顧客離れや株価下落を招いてしまったりすることもあります。
そこで、本コラムでは、企業活動とSNSに潜むリスクと対策を、Twitter(現X)日間トレンドワード5位にまで至った事案を数日で鎮静化させた経験のある弁護士が具体例を交えつつ解説します(全3回)。
リスクの類型と対応
法律に違反する投稿を行えば炎上は必至ですが、仮に直ちには法律に違反しない内容だったとしても、それが不適切な内容であれば、炎上してしまうことがあります。また、企業の不適切な行為や不備等を告発する投稿も同様に炎上リスクがあります。
そこで、法令に違反するかどうかにかかわらず、“特に陥りやすいSNS炎上リスク”に焦点を当てて、具体的なケースを検討します。
そして、望ましい“事前の対策と事後の対応”は、投稿等の種類によって大きくことなることもありますので、本コラムでは、具体的なケースごとに解説していきます。
※本コラムにおけるケースは一例であり、すべてのリスクを網羅するものではありません。また、トラブルを解決できることを保証するものでもありません。
目次
- ケース
1)著作権や肖像権などの権利を侵害するおそれのある投稿
2)景品規制や広告規制など各種法令に違反するおそれのある投稿
3)現代の価値観にそぐわない投稿
4)真偽不明な情報を含む投稿
5)少数派や特定の背景、経歴、考え方を持つ方などへの配慮に欠く投稿
6)賛否の議論が盛んな商品やサービスの利用やそれを肯定する投稿
7)特定の思想や自我が表れた投稿
8)不謹慎な投稿
9)過度な冗談、揶揄、憶測を呼ぶ投稿などモラルが疑われる投稿
10)不適切なハッシュタグやキーワード、画像その他のコンテンツを含んだ投稿
11)上記の内容を含んだ投稿のリポスト、不適切な投稿を行う者のフォロー - 投稿例
- 事前の対策・事後の対応
September 15th, 2025
公式の投稿・リポスト・フォロー等が不適切なケース
企業の配慮不足が原因となるケースが多いですが、SNS運用担当者のミス(ログインすべきアカウントの取違え投稿(いわゆる「誤爆」)など)によっても生じる場合があるので注意が必要です。
ケース
権利侵害に正面から該当する行為であり、故意ではないとしてもチェック体制の不備についての指摘は免れず、炎上リスクが非常に高いといえます。さらに、権利者からの損害賠償請求といった民事責任や罰金といった刑事責任を問われるおそれもあり、確実に回避しなければなりません。
こちらも法令違反行為として、故意でないとしても炎上リスクが非常に高いといえます。このうち広告規制は、主に虚偽広告や誇大広告を抑止するものですが、医薬品、化粧品や金融商品など、上乗せされた厳しい広告規制が敷かれている分野もありますので、十分なチェック体制を構築する必要があります。そして、これらの法令違反行為には、課徴金納付命令や是正命令、違反事実の公表、刑事罰など様々な制裁が設けられていることがありますから、上記同様、確実に回避する必要があります。
価値観は流動的であり、過去には黙認されていたことや見逃されてきたことであっても、現代では許されないということが多々あります(ハラスメント、性別観など)。こうした投稿は、意図的であればいうまでもありませんが、たとえ無自覚なものであったとしても価値観のアップデートがなされていない企業だと認識されてしまいます。
仮に有益な情報を届けたいという意図であったとしても、裏付けが不十分な情報を投稿することは、後に誤りであったことが判明した場合はもちろんのこと、真実であったことが判明した場合であっても、無責任・軽率な企業であるといった印象を与えてしまいます。
少数の反発であってもそれが火種となり、大規模な炎上を招くことがあります。結果としては多数の支持を得られる内容だったとしても、丁寧な検討が必要です。
新しい商品やサービスの中には、賛否両論があるものも少なくありません。他社の商品やサービスの利用や言及を行おうとする場合には、それらの懸念点や評判をきちんと検討しておくことが重要です。
特定の思想を表現すれば、反対の思想を持つ方々の反感を買ってしまいますし、運営者の人間味を表に出すことによって受け手に不快感や違和感を与えてしまうおそれがあります。確かに、無機質な公式アカウントに人間味を帯びさせたり親近感を抱かせたりする効果も期待できますが、リスクがあることを十分認識しておく必要があります。
過去に起こった事件や事故を思い起こさせるような投稿や近日のニュースを連想させるような投稿、災害や大きな事故が発生して間もない時期での明るい投稿などは大きなイメージダウンにつながります。災害発生から間もない時期などにおいてはインターネット通信の負担を少しでも減らすため、発信はなるべく自粛した方が穏当ですが、厳しい状況に置かれている方々に有益な情報を届けたい場合には、いつも以上に表現や投稿日時、タイミングに配慮して行う必要があります。
こういった投稿はエイプリルフールによく見られます。エイプリルフールの冗談とはいえども、ウソには違いありませんので、場合によっては、名誉毀損罪(刑法230条1項)、信用毀損罪(刑法233条)などの刑事罰や景品表示法違反といった法令違反に該当するおそれがあるなど、ユーモアの発揮と引き換えに重大なリスクがあることを理解する必要があります。また、ハッシュタグやキーワードに「#エイプリルフール」等と記載したとしても、表示が省略されてしまったり、切り抜かれてしまうことも多く、また、免罪符となるものではありません。さらに、度が過ぎた冗談(冗談であっても笑えない、本当のことだと受け取られてしまうなど)の場合には、もはや単なる悪質なウソと捉えられてしまい、エイプリルフールであれば許されるだろうという倫理観をもった企業と認識されてしまうおそれもあり、法令に抵触していなくとも大きなダメージにつながってしまいます。
ハッシュタグやキーワードは、便利な機能ではありますが、例えば、表示回数(インプレッション)を稼ぐ手段として利用するなど不適切な設定は敬遠されます。ハッシュタグやキーワード、画像やURLの掲載を行う場合には、これらも本文であるという認識をもってチェックする必要があります。
自社の投稿でなくても、不適切な投稿のリポストや投稿者のフォローも同じ影響を与えてしまうので注意する必要があります。また、自社の事業と関係ないリポストやフォローについても不適切と判断されるおそれがあります。同様に、炎上している投稿を連想させるような投稿も高リスクです。加えて、その時点では不適切な投稿を行っていない投稿者であっても、将来まではわかりませんので、注意が必要です。
そして、これらは、誤タップや誤クリックにより意図せず行ってしまうこともありますので、定期的にフォロワーやリポストのチェックを行っておくことが推奨されます。
投稿例
(いずれも実際にあった事案をもとにして作成した架空の投稿です。)
「男性の皆様への質問です。どうしても、家事は苦手ですか?」 |
「どうしても」といった文言や、回答欄の偏りが、男性は家事が苦手であるという誤った先入観を含んでおり不適切です。
「新商品の発売にあわせて社名を変更します!」 |
社名の変更はエイプリルフールの冗談のつもりでしたが、事実の発表とも受け取ることができる内容となっていたため、大きな混乱を招きました。
事前の対策・事後の対応
リスク回避のためには大きく、炎上等を回避するための事前の対策と、万一発生してしまった際の事後の対応の両方が重要です。 公式アカウント等の運営にあたっては、例えば、次のような対策・対応を行うことが考えられます。
事前の対策 |
事後の対応 |
|
|
|
|
事前の対策 | |
|
|
|
事後の対応 | |
|
※  :必要な対応
:必要な対応  :望ましい対応
:望ましい対応
避けるべき対応 |
||
|
|
第2回では、公式アカウント以外からの投稿について解説します。
以降の予定
第2回
従業員や関係者による不適切な投稿等がなされたケース
【ケース】
①従業員等による店舗等での不適切行為の投稿
②秘密情報や個人情報、取引先情報の投稿
③ステルスマーケティングの疑いがかけられてしまう投稿
【投稿例】
【事前の対策・事後の対応】
第三者による不適切な投稿等がなされたケース
【ケース】
①誤った情報の投稿
②第三者による店舗等での不適切行為の投稿
【投稿例】
【事前の対策・事後の対応】
第3回
告発的な投稿等がなされたケース
【ケース】
①企業内でのハラスメント被害や不当労働行為等を告発する投稿
②第三者による苦情等の投稿
【投稿例】
【事前の対策・事後の対応】
おわりに
本記事の内容は、公開日現在のものです。最新の内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。


 投稿の無言削除
投稿の無言削除