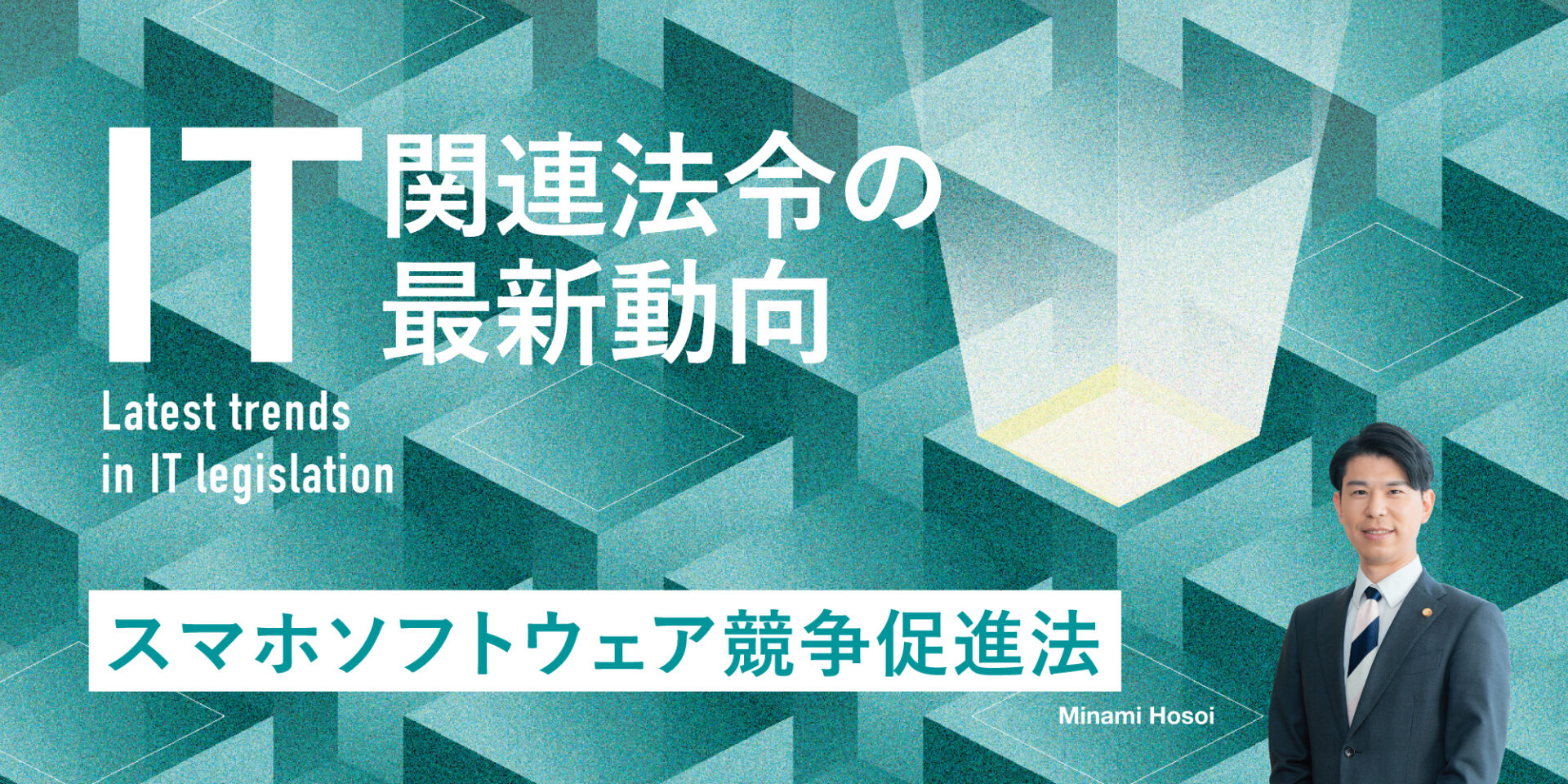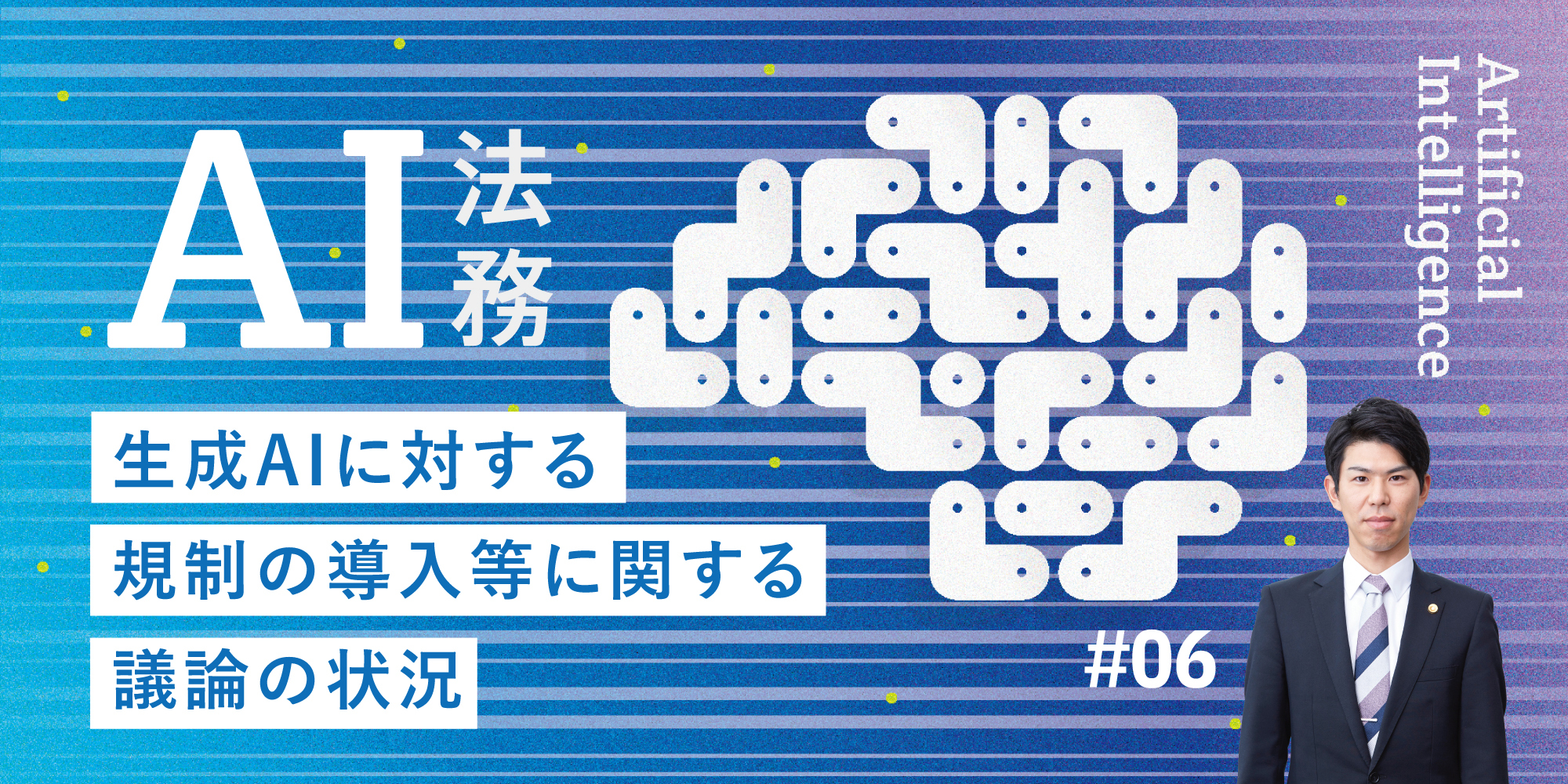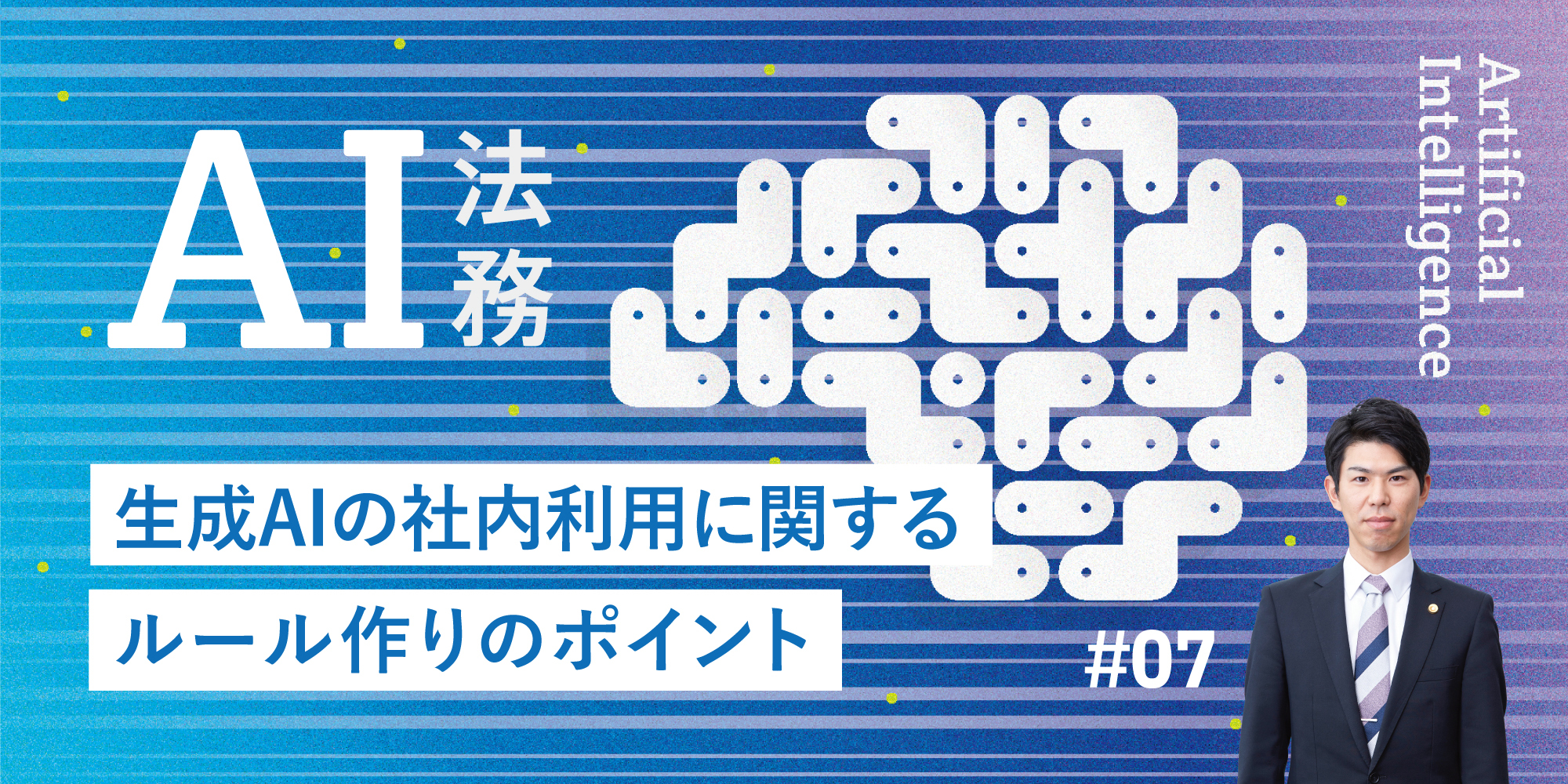IT関連法令の最新動向 スマホソフトウェア競争促進法
April 25th, 2025
概要
近年、デジタルプラットフォーマーが市場を独占していることが批判の対象となっており、既存の競争法の枠組みに加え、具体的な規制の枠組みを導入することが世界的に検討されています。例えば、EUでは、デジタル市場法(DMA)を制定し、巨大プラットフォーマーによる独占を防ぐための広範な枠組みを導入しています。これに対し、日本では、スマホアプリ市場というシングルイシューに絞り、個別的な規制を導入するアプローチを取り、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(略称:スマホソフトウェア競争促進法)を成立させました(2024年6月19日公布、施行日未定(2025年12月18日までに施行)※1)。また、公正取引委員会は、適用対象となる事業者の予見可能性を高めるため、2025年6月頃を目途にガイドラインを策定・公表することとされています。
スマホソフトウェア競争促進法の適用を受ける事業者は、公正取引委員会が指定する事業者(指定事業者)で、直近では以下の事業者が指定されています(2025年3月26日指定)。
※1 もっとも、既存の独占禁止法等による規制も可能です。実際、2025 年 4 月 15 日には、公正取引委員会が Google LLC に対し、Android のスマートフォンに Google の検索アプリをデフォルトで設定させていたこと等について、独占禁止法に基づく排除措置命令(不公正な取引方法(拘束条件付取引)違反)を行っています。 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250415_digijyo.html
指定した事業者の名称 | 当該指定に係る特定ソフトウェアの種類 | |
| 1 | Apple Inc.(注) | 基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ |
| 2 | iTunes株式会社(注) | アプリストア |
| 3 | Google LLC | 基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン |
(注)Apple Inc.とiTunes 株式会社は、共同してアプリストアを提供している。
出典:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250331_smartphone.html
このように適用対象となる事業者は限られているものの、この法律は、デジタル市場のプレイヤーとなるアプリ提供者などの中小事業者やスマホを利用する一般ユーザーの利益を保護する側面もあり、広く影響があるといえます。
コラム:デジタルプラットフォーマーによるデジタル市場の独占
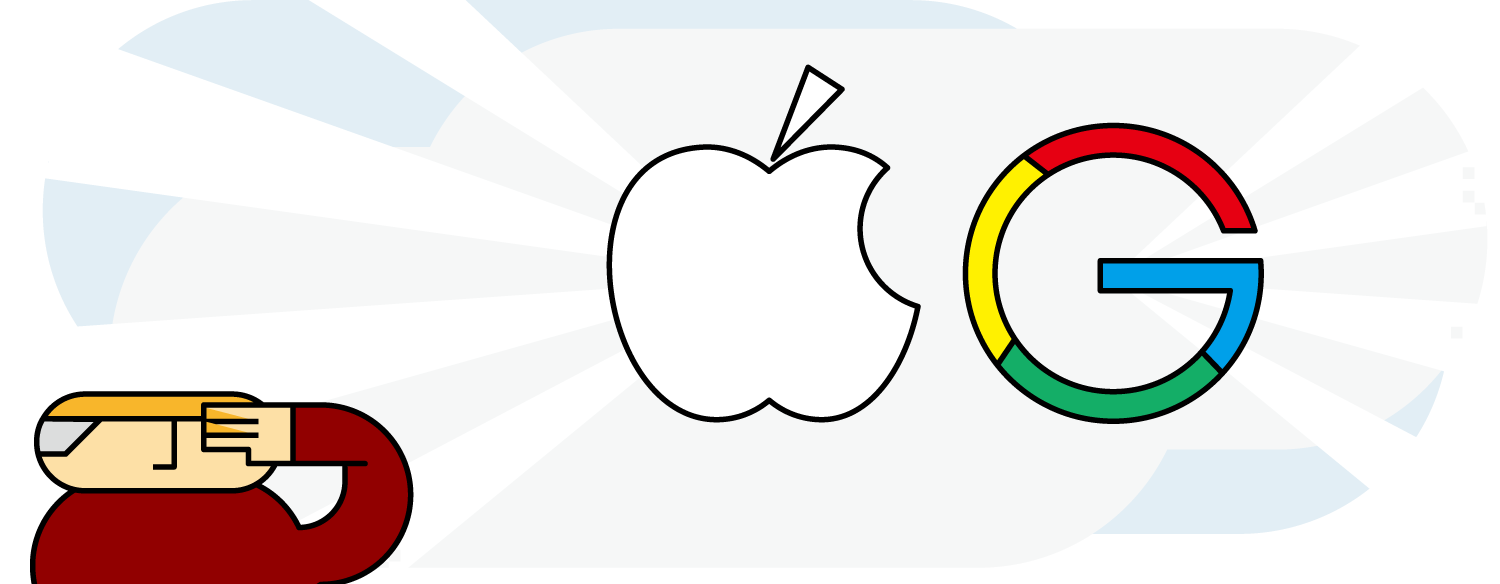
ご存じのとおり、デジタル市場は、Google、Appleなどのごく一部の事業者によって寡占化されている状況にあると指摘されています。では、なぜ、デジタル市場はこのように寡占化されやすいのでしょうか。 これを紐解くためのキーワードが、両面市場/多面市場と直接・間接のネットワーク効果です。
デジタル市場のサービスには利用者数の多さが、サービスの競争力の源泉となることがあります。例えば、LINEのようなコミュニケーションツールは、「みんなが利用しているプラットフォームである」ことに価値があり、利用者数が増えていくことで、雪だるま式に新たな利用者を呼び込んできたことにより発展してきました。デジタルプラットフォームが持つこのような効果は、直接ネットワーク効果と呼ばれています。
ところで、デジタルプラットフォーマーのサービス(Googleの検索サービス、YouTube、Xなど)の多くは、無料で利用することができます。当然ながら、全くの無料では事業は成立しませんので、背後には無料のサービス提供を成り立たせる仕掛けがあります。たとえば、検索サービスでは、検索の利用者というユーザーがいるのとは別に、検索サイトに広告を出稿する広告主が存在します。このように、2つの顧客(市場)を持つサービスの特性を両面市場と呼んでいます。さらに、検索の利用者の行動履歴を解析したデータを購入するECサイトの運営者が存在したりするなど、3つ以上の市場が成り立つこともあるため、多面市場と呼ばれることもあります。
このような、両面市場/多面市場では、ある市場の利用者が増えることが、別の市場のサービスの価値を高め、利用者を増やす効果を生むことがあります。例えば、検索サービスでは、検索の利用者が増えれば、広告主にとってより魅力的な媒体となり、広告料収入が増えます。その増えた収入は、検索サービスをより魅力的なものにする投資に利用され、検索の利用者がさらに増えるという関係性があります。このような、市場をまたいで雪だるま式にサービスが肥大化していく効果は、間接ネットワーク効果と呼ばれています。
このようなネットワーク効果を背景に、デジタルプラットフォームサービスは新規参入が非常に困難な市場になってしまっており、巨大プラットフォーマーによる中小事業者や、ひいては一般の利用者に対する優越的な地位が問題となり、規制の必要性が叫ばれているのです。
規制の内容
スマホソフトウェア競争促進法の内容は多岐にわたりますが、主要な内容は、以下の通りです。
(1)禁止事項
スマホソフトウェア競争促進法は、特定の行為類型を形式的に禁止することによって、市場に悪影響が生じたかといった実質面を考慮することなく違反を認定できるような仕組みをとっています。これにより、独占禁止法と比較して、より迅速な執行が期待されています。 具体的には、以下の事項が禁止されます。
- 取得したデータの不当な使用の禁止(5条)
- アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止(6条)
- 他のアプリストアの提供妨害の禁止(7条1号)
- モバイルOSの機能の利用妨害の禁止(7条2号)
- 他の課金システムの利用妨害の禁止(8条1号)
- アプリ内での情報提要やリンク表示の制限の禁止(8条2号)
- 他のブラウザエンジンの利用妨害の禁止(8条3号)
- 自社のソーシャルログインの利用強制の禁止(8条4号)
- 検索結果の表示における自社優遇の禁止(9条)
- 公正取引委員会への報告を理由とした不利益取扱いの禁止(15条2項)
例えば、「他のアプリストアの提供妨害の禁止」について、見ていきましょう。これまでAppleは、Appleが提供するアプリ市場「App Store」を経由しないアプリのダウンロードを機能上制限してきました。これにより、事前にAppleが審査したアプリのみが入手可能となることで、安全性が十分であると判定されたアプリのみが流通し、セキュリティ上のリスクを回避するという利点がありました。とはいえ、「App Store」が市場を独占していては、アプリの提供者が支払う手数料の額について競争が働かず、問題があります。そこで、スマホソフトウェア競争促進法は、他のアプリストアの提供の妨害を原則として禁止しつつ、指定事業者は、セキュリティの確保、プライバシーの保護、青少年の保護等の目的のために「必要な措置」を講じることができるとされています(必要な措置としては、例えば、他のアプリストアにセキュリティ審査に関する一定の条件を課すことなどが想定されます。)。
(2)措置の義務付け
また、スマホソフトウェア競争促進法は、事業者間の公正かつ自由な競争を確保するため、指定事業者に対して、以下の措置をとることを義務付けています。
- 取得データの使用条件等の開示に係る措置(10条)
- 取得データの利用者に対する移転に係る措置(11条)
- デフォルト設定の変更、選択画面の表示に係る措置(12条1号イ等)
- 追加インストールの同意、アンインストールに係る措置(12条1号ハ・ニ)
- 仕様変更等の開示、期間の確保等に係る措置(13条)
例えば、「デフォルト設定の変更、選択画面の表示に係る措置」についてみると、モバイルOS等の提供にあたり、自社のアプリ等がデフォルトに設定されていることが一般的(例えば、ブラウザでいえば、iOSのSafari、Android OSのChrome)ですが、他社のアプリへの変更が面倒であると、他社は競争上不利になってしまいます。そこで、デフォルト設定を簡易な操作で変更できることや、他の選択肢を示す選択画面を表示するなど、ユーザーの選択を容易にする措置が義務付けられます。
(3)違反行為に対する措置
指定事業者がスマホソフトウェア競争促進法に違反した場合、公正取引委員会は違反を是正するため、排除措置命令や課徴金納付命令を出すことができます。課徴金算定率は、違反行為に係るサービス等の売上額の20%(10年以内に違反行為が繰り返された場合は30%)と、かなり高い算定率となっています。
最後に
IT法・競争法分野に関しては、国内外において、日々、大きな変化が生じており、インターネットを通じて得られる情報が最新でない場合もあります。したがって、事業活動の中で具体的な問題が生じた場合は、是非お早めに当該分野に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
本記事の内容は、公開日現在のものです。最新の内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。