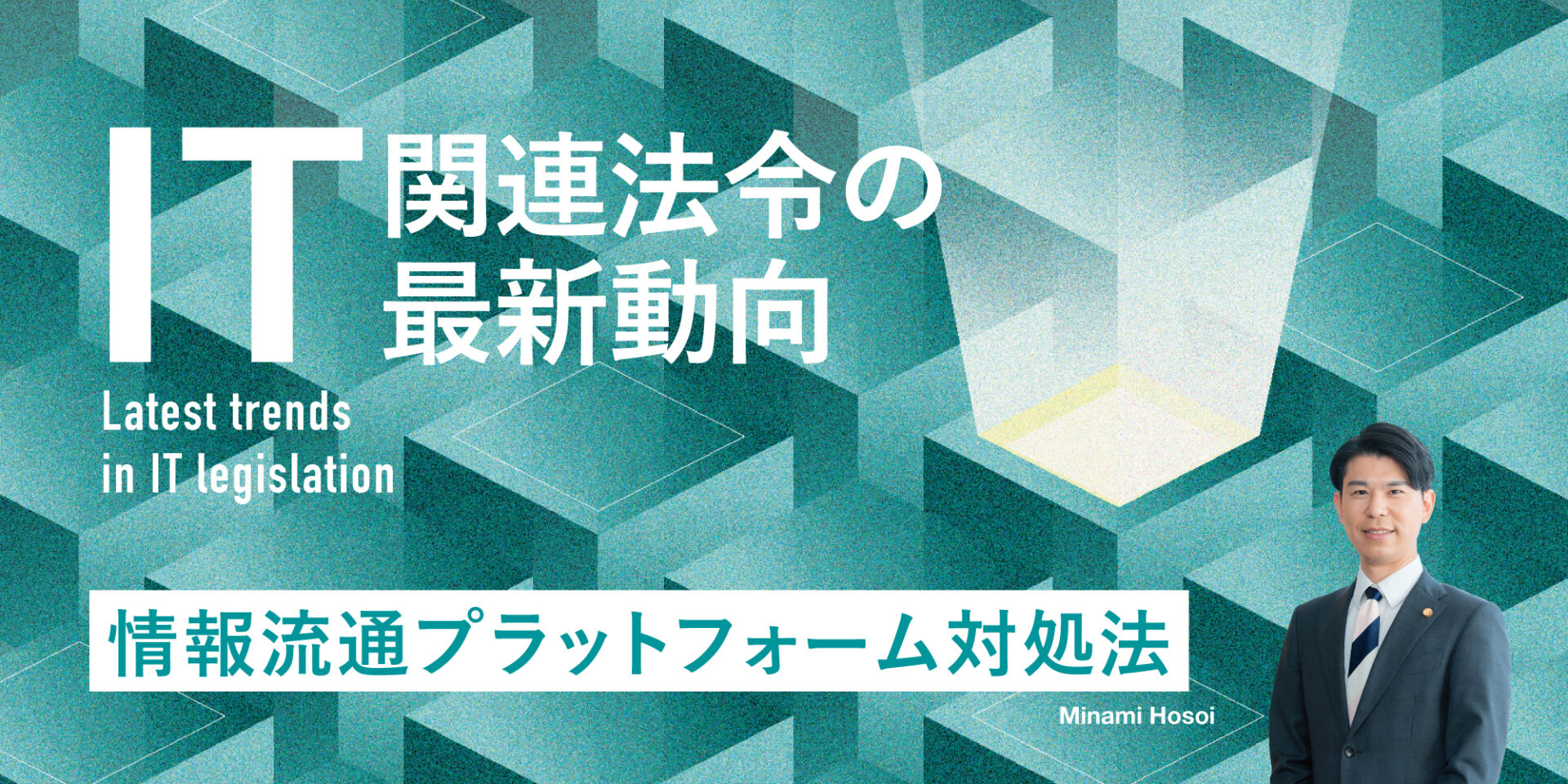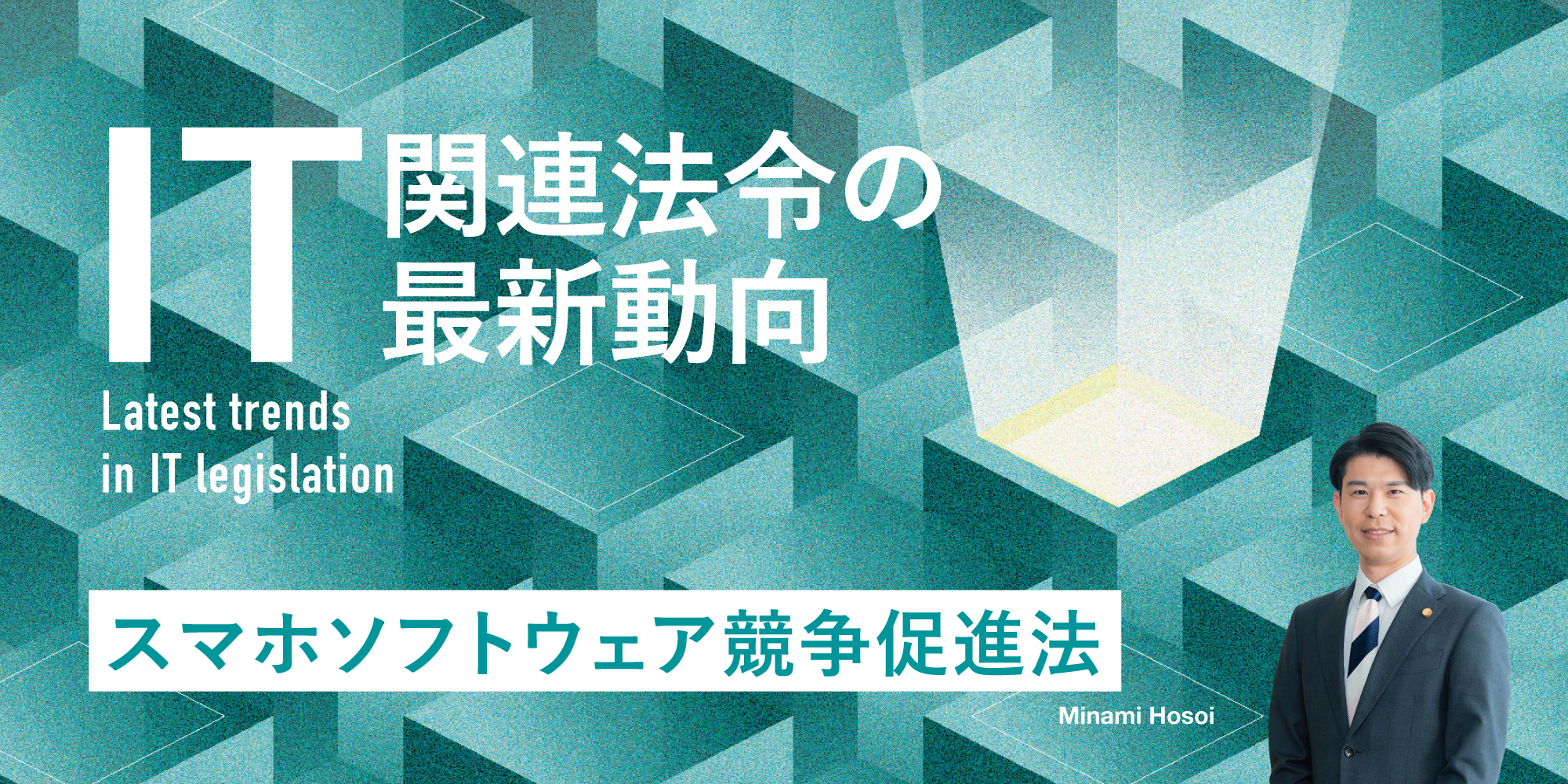IT関連法令の最新動向 情報流通プラットフォーム対処法
May 25th, 2025
概要
2024年5月17日に公布された「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(以下「情報流通プラットフォーム対処法」といいます。)が、2025年4月1日に施行されました。情報流通プラットフォーム対処法は、誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大手SNS事業者等の一定の規模を有する大規模プラットフォーム事業者に対し、①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置を義務づけること等を内容とするものです。なお、情報流通プラットフォーム対処法は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称:プロバイダ責任制限法)を改正したもので、内容に即して法律の名称も改められました。
本改正は、「プラットフォームサービスに関する研究会」による2020年8月「インターネットの誹謗中傷への対応の在り方に関する緊急提言」や、2024年1月「第三次とりまとめ」による提言を受けて行われたものです。プラットフォーマーにおいて、削除等の対応を迅速化し、また削除基準等の運用状況を透明化することが本改正の狙いです。
すなわち、プロバイダ責任制限法の下では、誹謗中傷等の情報の削除等につき、事業者が対応窓口を置いていない、あるいはなかなか対応してくれないために、被侵害者がやむなく法的措置をとるケースが多く存在していました。このような措置を強いられることは、解決までに要する時間・費用の面から見て、救済が不十分であると言わざるを得ません。
この改正により、大規模プラットフォーム事業者の自主的な対応により、誹謗中傷等に対するより簡易・迅速な被害救済の実現が期待されます。
なお、本改正に関しては、総務省が2025年3月11日付けで、以下のガイドラインを制定しており、これらも参考になります。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン
違法情報ガイドライン(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン)
改正前のプロバイダ責任制限法の概要
本改正の概要をご説明するに先立ち、改正前のプロバイダ責任制限法の概要をご説明いたします。なお、以下の内容はいずれも本改正後(すなわち情報流通プラットフォーム対処法)においても維持されています。
(1)損害賠償責任の制限(第3条)
プロバイダ責任制限法は、その名の通り、事業者の責任範囲を限定することを本来意図したものでした。すなわち、特定電気通信(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)により有害情報が流通した場合に、特定電気通信役務提供者(掲示板の管理者、ホスティングプロバイダ、経由プロバイダ等)は、当該情報を流通させていることについて損害賠償責任(不作為責任)を追及されるおそれがあります。他方で、特定電気通信役務提供者が当該情報について削除等の送信防止措置を講じたときは、発信者から損害賠償責任(作為責任)を追及されるおそれがあります。特定電気通信役務提供者が、このようなジレンマに陥り適切な対応ができなくなることを避けるため、プロバイダ責任制限法は、有害情報を流通させていること、または送信防止措置を講じたことについて、一定の場合に特定電気通信役務提供者を免責する規定を設けていました。かかる規定は、表現の自由の不当な侵害を抑止するとともに、削除されるべき情報については迅速かつ適切に対応がなされることを促す機能を有しているといえます。(2)発信者情報の開示請求(第5条)
この制度は現在ではかなり広く知られるものとなっていますが、有害情報の流通によって権利を侵害された者は、①権利侵害の明白性と、②開示を受けるべき正当な理由があるときは、特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報の開示を請求することができるという請求権が定められています。(3)新たな裁判手続(第8条~第19条)
従来、上記の発信者情報の開示請求は、通常の民事訴訟や保全手続(仮処分)によって実現されていました。しかし、インターネットの仕組み上、異なる相手方に対し複数回にわたり申立てが必要となるなど、開示を求める側の実務的な負担が大きいことが問題視されていました。そこで、2021年改正で、一連の手続で発信者情報の開示手続を完結できるように、新たな裁判手続(非訟手続)で設けられました。この手続は、開示請求の実務の流れを踏まえて設計された手続で、開示命令、提供命令、消去禁止命令から構成されます。本改正の内容
先に述べたとおり、情報流通プラットフォーム対処法においては、一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に対して、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化および送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を課す規律が追加されています。以下、詳しくご説明いたします。
対象となる大規模プラットフォーム事業者の範囲
情報流通プラットフォーム対処法において追加された義務の対象となる「大規模プラットフォーム事業者」(法文上の表現では「大規模特定電気通信役務提供者」)は、月間の利用者数(1,000万人以上)の基準等により、総務大臣が指定することとなっています。2025年4月30日時点で、総務省は、以下の事業者を「大規模プラットフォーム事業者」として指定しています(情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定)。
大規模特定電気通信役務提供者 | (参考)サービス名 |
| Google LLC | YouTube |
| LINEヤフー株式会社 | Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、 LINEオープンチャット、LINE VOOM |
| Meta Platforms, Inc. | Facebook、Instagram、Threads |
| TikTok Pte. Ltd. | TikTok、TikTok Lite |
| X Corp. | X |
大規模プラットフォーム事業者の義務の概要
大規模プラットフォーム事業者に指定された際に義務付けられる事項は多岐にわたりますが、大要、以下のような内容となっています。
❶ 大規模プラットフォーム事業者による届出(第21条) |
指定を受けた事業者は、3ヶ月以内に所定の事項を総務大臣に届け出る必要があります。 |
❷ 被侵害者から申出を受け付ける方法の公表(第22条) |
大規模プラットフォーム事業者は、被侵害者が侵害情報送信防止措置(例えば、侵害情報を削除すること等をいいます。以下同じ。)を講ずるよう申出を行うための方法を定め、公表しなければなりません(第1項)。 |
この「方法」は、次の 1~3 に適合するものである必要があります(第2項)。
|
❸ 侵害情報に係る調査の実施(第23条) |
大規模プラットフォーム事業者は、被侵害者から❷の「方法」に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません。 |
❹ 侵害情報調査専門員(第24条) |
大規模プラットフォーム事業者は、❸の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員を一定数以上選任しなければなりません。 * 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する 法律における大規模特定電気通信役務提供者の義務に関するガイドライン」によれば、侵害情報調査専門員は、削除等を実施する職員が判断に迷った際に当該職員からの上申を受けて、より専門的な調査を行う役割があるため、大規模プラットフォーム事業者のサービスの特性を十分に理解するとともに、法令や文化的・社会的背景に明るい人材である必要があり、具体的には、弁護士等の法律専門家や日本の風俗・社会問題に十分な知識経験を有する自然人が考えられるとされています。 |
❺ 申出者に対する通知(第25条) |
大規模プラットフォーム事業者は、❸の調査の申出があったときは、調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から7日以内(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第16条)に、次の 1,2 の事項を申出者に通知しなければなりません(一定の例外あり)。
|
ただし、大規模プラットフォーム事業者は、調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき、調査を専門員に行わせることとしたとき、その他やむを得ない場合は、当該申出を受けた日から7日以内には、その旨を申出者に通知すれば足ります。この場合、大規模プラットフォーム事業者は、調査結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後遅滞なく、上記1,2の事項を申出者に通知することとなります。 |
❻ 送信防止措置の実施に関する基準等の公表(第26条) |
大規模プラットフォーム事業者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の 1〜3 のいずれかに該当する場合のほか、自ら策定・公表する基準に従う場合、送信防止措置を講ずることができます。
この規定は、大規模プラットフォーム事業者が、自己が提供するプラットフォームでの情報の流通については、自ら策定・公表する基準に従い、送信防止措置(投稿の削除等)を行うことができることとすることで、大規模プラットフォーム事業者による基準の策定、公表を促すものです。 |
上記の基準を公表している大規模プラットフォーム事業者は、おおむね1年に1回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならないとされています。 この規定は努力義務にすぎないものの、事業者が定めた基準の運用状況の透明化を促す狙いがあります。 |
❼ 発信者に対する通知等の措置(第27条) |
大規模プラットフォーム事業者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の 1,2 のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(通知等の措置)を講じなければなりません。この送信防止措置が、❻の基準に従って講じられたときは、その理由の中で、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければなりません。
|
❽ 措置の実施状況等の公表(第28条) |
大規模プラットフォーム事業者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次の 1〜4 の事項を公表しなければなりません。
|
本記事の内容は、公開日現在のものです。最新の内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。